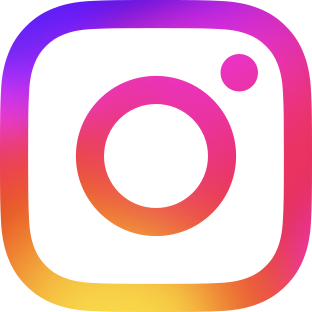英語4技能いよいよ中学校で導入
こんにちは塾長松本です。
今日は英語の4技能がいよいよ中学校で導入さえれると言う話です。
戦後の大学入試の英語の試験は「読む」と「書く」が中心でした。
センター試験の前身の「大学共通一次学力試験」(通用共通一次)が登場しても英語試験の内容は「読む」と「書く」が中心でした。
しかし、センター試験が1990年にスタートして2006年からセンター試験の英語にリスニングが導入されることなり、英語の試験は3技能(「読む」「書く」「聞く」)になったわけです。
大学入試が3技能ですから当然高校入試もそれに倣って3技能になりました。高校入試にもその後リスニング試験が導入さレます。
しかし、国際化が進むにつれて、日本人が英語が話せないと言うことが、「国民的な教育の課題」として捉えられる様になってきます。
ここで日本人の中にも誤解が生じたことを指摘しておかなくてはいけません。
それは 「日本人は読む英語はできるので英語は分かっている。しかし、なぜか日本人は英語で話せない。日本人にとっての英語の問題とは英語で話せないということである。」という考え方が一般に広まったことです。
本当にそうでしょうか。
ちょっと難し問題にはなるのですが、日本人が文法的に正しいと思って使っている英文のなかに英語では絶対使わない英語がたくさんあるというのも事実なのです。
例えば
There is my cat on the desk.
この文章は一見正しそうですが、絶対使われない英語です。つまり文法的に誤っています。
ただしい英文は
My cat is on the desk.
です。
最初の英文は
There is a cat on the desk.
ならあっています。
つまり There is の構文の時 不特定の a cat は使えるのですが 特定された my cat は使えないのです。
果たしてこれは事実でしょうか。
例えば次の様な日本文を英文に訳すとどうなるでしょうか。
『難しくないと思います。』
ほとんどの日本人の訳文
I think it is not difficult.
しかしこれはネイティブは絶tたい
そこで4技能の登場です。
2020年の大学入試改革において、英語については、それまでの三技能(「読む」「書く」「聞く」)に「話す」加えてえ四技能で試験をすることになったわけです。
英語教育の専門家立教大学名誉教授の鳥飼玖美子さんは最初から大学入試に英語の4技能を採用することにのに疑問を呈している人のうちの一人でした。